マイホーム購入前に押さえておきたい不動産用語
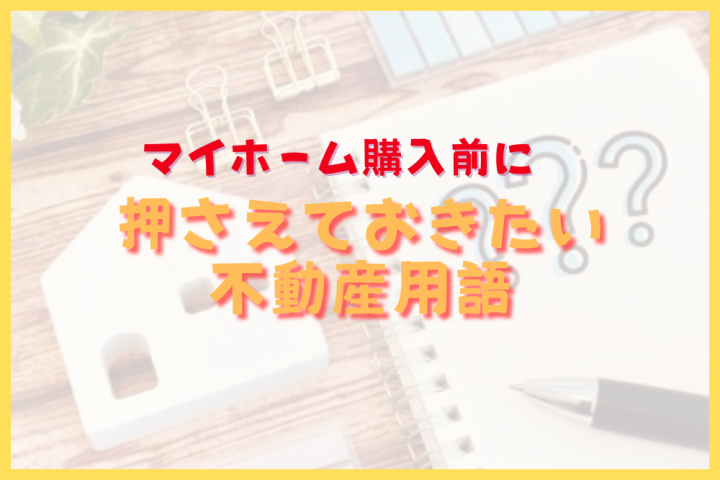
マイホーム探しを進めていくなかで、「販売図面」と「間取図」または、担当営業の人との打ち合わせをしてみると不動産用語に「え?どんな意味??」となることもありますよね。
マイホームの購入は一生に一度の大きな買い物です。よくわからないままマイホームを購入するなんてことは絶対にしたくない!と思われている方。
今回はマイホーム探し中、またはこれからマイホームを契約する時に知っておくと安心の用語・略語についてお伝えしていきたいと思います。
◇基本編
まずは、一般的な居室の間取りから。最近ではアルファベット表記の間取図も少なくありません。
馴染みのある用語をおさらいしつつ、初めて見たときには、きっと戸惑う用語を解説します。

◆畳・帖
部屋の広さの単位。1畳(帖)は1.62㎡です。
◆Ent
Entrance(エントランス)。玄関。
◆HALL
ホール。玄関から居間までの廊下や広間。
◆LDK
Living Dinning Kitchen(リビング ダイニング キッチン)。居間(リビング)と食事をするスペース(ダイニング)、そして台所(キッチン)がひと続きになっている部屋。
◆DK
Dinning Kitchen(ダイニング キッチン)。食事をするスペース(ダイニング)と台所(キッチン)が一緒になっている部屋。
◆K
Kitchen(キッチン)。台所。
◆S
Service Room (サービスルーム)。またはstorage Room(ストレージルーム)。採光が不足して居室として認められない部屋。納戸やフリースペースとして使える。
◆OL
Open Living(オープン リビング)。吹き抜けやバルコニーなどと一体化したリビング。
◆PL
Private Living(プライベート リビング)。来客用のリビングのほかに設けられた、家族や夫婦だけで使用するリビング。
◆MBR
Master Bed Room(マスター ベッドルーム)。主寝室。
◆RF
Roof floor(ルーフ フロアー)。ロフトのこと。そのまま「LOFT」と記載されることもある。
◆SR
Sun Room(サンルーム)。日光を取り入れるため、ガラス張りにした部屋。
◆DEN
「ほら穴」という意味の英語で、部屋にするには狭いが、こもれるスペースで、書斎や趣味を楽しむためのエリアなどに使われる。
◆Void
「吹き抜け」のこと。間取り図では、「Void」という用語の他に、どこからどこまでが吹き抜けかが分かるように「×」印で描かれている。
◆勾配天井
勾配、傾斜をつけた天井のこと。通常の平らな天井よりも天井高が高くなり、開放感がある。
◆折上天井
天井の中央を周りの部分よりも一段高く仕上げた形状の天井。
◆折下天井
天井の一部を回りの部分より一段下げて仕上げた形状の天井。
◆ファミリー玄関
来客用の玄関と普段家族が使う玄関を分けたスタイル。
◇キッチン・水回り編
続いて、家事動線を考える上でも重要な水回りの用語についてご紹介していきます。
◆R
Refrigerator(冷蔵庫)。「R」または、冷蔵庫の「冷」と書いてある場合もある。
◆W
Washing Machine Place(洗濯機置き場)。「W」または、洗濯機の「洗」と書いてある場合もある。
◆WC/Lav
Water Closet(水洗式トイレ)。英国式に「トイレット」の「T」と書いていることもある。あるいは、わかりやすく便座のイラストが描いてある場合も多い。
そのほかのトイレの表記として、最近は「Lav(Lavatory)」と表記する間取図も。
◆UB
Unit Bath(ユニット バス)。工場で成型された天井、浴槽、床などがセットになっていて、現場に搬入して組み上げるタイプの浴室。
◆SK
Slop Sink(スロップシンク)。掃除用の流し。バルコニーなどについている底の深い大型の流しのことで、人気が高まってるランドリールームに設置するケースも増えている。
◆SB
Shoes Box(シューズ ボックス)。靴の収納スペース、靴箱。
◆SIC
Shoes-in Closet(シューズ イン クローゼット)。SBよりも広い靴の収納スペース。靴だけではなく、ベビーカーやアウトドア用具なども収納可能なスペース。
※間取図チェックの際は、風通しがよさそうか、換気設備の設置は必要かなど、カビや匂い対策についてもしっかり考えておきたいポイント。
◆CL
Closet(クローゼット)。衣類をしまう洋風のスペース。
◆WIC
Walk-in-closet(ウォーク イン クローゼット)。歩いて入るほどのスペースがあるクローゼット。クローゼットの内部には棚や洋服掛けなどが設置されていて、収納力抜群。
◆WTC
Walk-threw Closet(ウォーク スルー クローゼット)。2つの開口部を持つ、通り抜けができるクローゼット。主に居室と居室の間に設けられ、どちらの部屋からも出入りが可能。
◆FC
Family Closet(ファミリー クロゼット)。家族で共用する収納を、特にファミリークローゼットと呼ぶ場合もある。ランドリールームや玄関に隣接して設置するケースも増えている。
◆Pantry
Pantry(パントリー)。キッチンに隣接して設置し、食料品の貯蔵や、食器、配膳室。またちょっとした事務用カウンターを設置する場合もある。
◆Sto
Storage(ストレージ)。倉庫・貯蔵室・納戸。
◆グルニエ
「屋根裏部屋」を表すフランス語。天井と屋根の間のスペースを利用した小部屋。
◇設備・その他編
◆BP
Bicycle Poarch(バイシクル ポーチ)駐輪場。
◆MB
Meter Box(メーター ボックス)。ガス、電気、水道のメーターを設置するスペース。
◆PS
Pipe Space・Pipe Shaft (パイプ スペース・パイプ シャフト)。上下水道管やガス管などの配管スペース。
◆DS
Duct Space(ダクト スペース)。全館空調を採用している家などで、空気を送るダクトを通すのに必要なスペース。
◆UP・DN
複数階の建物で、階段の上り始めを「UP」、下り始めを「DN」として表す。平面の間取りでは、どちらが階段の上側なのか下側なのか、一見したところでは分かりにくいこともあるため、このように表記されている。
◆CF
Cushion Floor(クッション フロア)。表面に塩化ビニールを用いた床材。水回りや賃貸物件で使用されることが多い。
◆インナーバルコニー
バルコニー部分が建物の内側に引っ込んでいる形状のバルコニー。 広くとられた屋根付きの空間のため、屋外なのに天候の影響を受けにくいので、幅広い用途で利用できる。
◆ルーフバルコニー
下の階の屋根の上にあるバルコニー。一般的にルーフバルコニーは広く開放感があり、日当たりも良いものが多い。
◆アルコーブ
廊下や部屋などにある壁の一部をくぼませて作る独立したスペースのこと。語源は英語の「alcove」で、廊下や居室にある「くぼみ」を意味する。
◆ディスポーザー
生ゴミを粉砕しながら下水に流す処理設備。衛生面に優れ、生ゴミ処理の手間もかからないため、人気のシステム。
◇土地編
◆市街化区域
街を活性化するための地域。
人々が住みやすくなるように、インフラの整備などが積極的に行われる。
市街化区域では、13種類の用途地域や道路、公園、下水道などの都市施設が都市計画で定められる。
◆市街化調整区域
市街化を抑制する地域。
人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリア。
「市街化調整区域」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆11号区域
都市計画法第34条第11号に基づく区域。
市街化調整区域の中でも一定の集落を形成しており主要な道路や排水施設がほとんど整備された区域を指定することにより、住宅や小規模店舗(延床面積150m²)などが立地可能となる区域。
※法令の細かな条件は各市区町村の役場にお問い合わせください。
◆12号区域
都市計画法第34条第12号に基づく区域。
市街化調整区域内での建築物の建築の制限にかかわらず、一定の基準を満たすことで建築物の建築が可能となる区域。
※法令の細かな条件は各市区町村の役場にお問い合わせください。
◆用途地域
都市計画法によって建築できる建物の種類や土地の用途について決められているエリア。
「用途地域」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆旗竿地
竿に旗がついたような形の土地のこと。
「旗竿地」以外にも「敷地延長(敷延)」や「路地状敷地」と言われることも。
「旗竿地」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆仮換地
土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定された土地のこと。一般的には将来そのまま換地となる予定の土地。
◆換地
土地区画整理事業の工事後、区画整理前の土地の代わりに交付される宅地のことをいいます。
◆公道(市道)
国や地方自治体の管理のもと、公共で使われている道路のこと。
高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道など道路法上の道路のほか、都市計画事業などによって築造された道路がある。
◆私道
民間の個人や法人が所有している道路のこと。
特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。
◆位置指定道路
「建築基準法上の道路」として市町村等の認可を受けた道路。その多くは私道。
◆協定道路
建築基準法上の道路とは異なり、各都道府県や各市町村に設置されている建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある通路。
「建築基準法第43条但し書き道路(43条2項2号許可)」「但し書き道路」などとも呼ばれる。
土地を分筆して宅地分譲や新築建売住宅を販売する際に、協定道路が作られることが多い。
◆2項道路
「建築基準法第42条第2項」の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。「みなし道路」とも呼ばれる。
建築基準法施行前から使われている幅員4m未満の既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされる。
◆セットバック
「後退」を意味し、不動産業界や建築業界では敷地や建物を道路や隣地などの境界線から離す(後退させる)ことをいう。
敷地に接している前面道路が幅員4m未満の場合の宅地に建物を建てるときは、道路の中心線から2m以上後退させる。
◆建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。建築面積を敷地面積で割って算出する。
建築基準法に基づき、用途地域に応じて建ぺい率が制限されている。
建ぺい率=建築面積/敷地面積×100
◆容積率
建物の延べ面積(延床面積)の敷地面積に対する割合のこと。延べ面積を敷地面積で割って算出する。
建築基準法に基づき、用途地域に応じて容積率が制限されている。
容積率=延べ面積/敷地面積×100
◆地区計画
それぞれの地区の特性に応じて、良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画のこと。建築物等の用途の制限や建築物の敷地面積の最低限度などが定められています。
◆地役権
一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のこと。
たとえば、『他人の土地を通ったほうが駅に出やすい』など、通行のために他人の土地を利用する場合に地役権を設定するケースがある。これを通行地役権と呼ぶ。
◇契約用語編
◆重説
重要事項説明書の略語。
不動産売買契約を結ぶ前に「買主」に対し不動産仲介会社が「取引物件」や「取引条件」について、文字通り契約に関する重要な事柄書面を用いて詳しく説明すること。
「重説」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆手付
契約成立の際の手付金を売買契約に際して買主から売主に対して交付される金銭のこと。
一般的には契約の成立を証するための「証約手付」を意味している。
◆解約手付(手付解除)
買主は手付金を放棄すれば(手付流し)、また売主は手付金の2倍の金額を買主に支払えば(手付倍返し)、契約を解除できる。
◆違約手付
買主か売主のどちらかに債務不履行があった場合に、手付金が違約金として、損害賠償とは別に相手方に没収されると定めるケースがある。
◆契約不適合責任
購入した住宅の状態が契約した内容と異なっていた場合に、売主に問うことができる責任のこと。
「不動産登記」についてはこちらの記事もご覧ください。
▶新築を購入したら不動産登記が必要!?費用はどのくらいかかる?
◆損害賠償
違法行為によって損害が生じた場合に、その損害を填補すること。
◆抵当権
住宅ローンなどでお金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のこと。
◆表題登記
登記されていない土地や建物の表題部を新たに作成する登記。
◆所有権移転の登記
既に所有権の登記がある不動産について、所有権が移転された場合に行う登記。
「不動産登記」についてはこちらの記事もご覧ください。
▶新築を購入したら不動産登記が必要!?費用はどのくらいかかる?
◆借地権
建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利を「借地権」という。
借地権者(借り主)は定期的に地主に地代を払う義務を負う。借地権には、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類がある。
◆頭金
不動産における頭金とは、不動産価格から住宅ローン借入額を差し引いた部分の金額。
たとえば、3,000万円の住宅に対して、頭金を500万円支払うと残りの2,500万円を住宅ローンで支払うことになる。
一般的には預貯金や親族からの贈与を頭金にするケースが多い。
◆決済
不動産における決済は、買主との間で締結した売買契約に基づいて、取引を完了させる最後の段階であり、「残代金の授受」と「物件の引渡し」を行う。
決済を行うことによって、不動産の売買取引が完了する。
◆金消
金銭消費貸借契約の略語。
借主が、貸主から金銭を借り入れ、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。
住宅ローンを借りるとき銀行などの金融機関と結ぶ「住宅ローン契約」と呼ばれる契約は、この「金銭消費貸借契約」と「抵当権設定契約」をセットにしたもので、「金銭消費貸借抵当権設定契約」とも呼ばれている。
◆インスペクション
調査、検査、視察、査察などを意味を持つ英単語。
住宅におけるホームインスペクションは、建築士や住宅診断士など詳しい専門家が、住宅の劣化レベル、工事不備などを診断し、その改修規模や概算コストの目安を算定し、客観的な立場でアドバイスをすること。
「インスペクション」についてはこちらの記事もご覧ください。
◇住宅ローン編
◆元利均等返済
毎月返済額などが一定になるように、「元金」と「利息」を計算した返済方法。
返済開始当初の返済額が少ないことや、毎月の返済額が一定であるため返済計画が立てやすいことも特徴。
◆元金均等返済
毎回の返済額に占める元金の返済分を一定とし、利息額は、各回の元金の額に金利を掛けた分を支払う方法。
利息額は借入残高に金利をかけて計算するため、返済が進むにつれ支払う利息の額も減っていくことが特徴。
◆変動金利
返済の途中でも市場金利に合わせて金利が変動するタイプのローン。
一般的に、年に2回金利の見直しがあり、5年に1回返済額が見直される。
◆固定金利
借入時の金利が返済開始から終了まで固定されているタイプのローン。
月々の返済額が常に一定で、長期的なライフプランが立てやすい。
「住宅ローン」の基礎知識についてはこちらの記事もご覧ください。
▶住宅ローンは何年で組んだらいい?~平均値でみる住宅ローン~
◆フラット35
住宅金融支援機構が提供する、民間金融機関と提携した長期固定金利型住宅ローン。
多くの金融機関では、団体信用生命保険の加入が義務付けられているのに対して、フラット35では加入は任意。
融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。
「フラット35」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆フラット35S
「フラット35」の一種で、住宅が一定の基準を満たすと、当初の金利が、ベーシックタイプフラット35のものより、一定期間引き下げられるというもの。
フラット35の技術基準に加え、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性、バリアフリー性の基準のうち1つ以上を満たすことが条件となっている。
◆住宅ローン控除
マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度のこと。
新築住宅の場合、控除期間は原則13年間。(中古住宅の場合は10年間)
控除額は年末の借入金残高の0.7%となっている。この特別控除の適用は、2025(令和7)年12月31日までである。
「住宅ローン控除」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆住宅ローン事務手数料
住宅ローンを契約して借入する際に、金融機関に対して支払う手数料。
金融機関によって「融資事務手数料」や「取扱手数料」などと呼び方が異なり、借入金額などの条件によって支払う金額も変化する。
◆住宅ローンの保証料
住宅ローンの連帯保証人を立てる代わりに保証会社に支払う費用。
万が一、住宅ローンの契約者が返済を続けることができなくなった場合、保証会社が金融機関へローン残額を支払う仕組みとなっている。
なお、保証会社が契約に基づきローン残額を支払ったとしても、ローン契約者に対する債権が金融機関から保証会社に移るだけですので、返済義務は消失しない。
「諸費用」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆団信
団体信用生命保険の略語。
住宅ローンを契約している人が死亡または高度障害状態になった場合、その保険金で住宅ローンの残額が完済される保険。
「団信」についてはこちらの記事もご覧ください。
◆繰り上げ返済
住宅ローンの定期的な返済とは別に、残債の一部または全部を返済する方法。
全額が元金の返済に充当されるため、利息を減らす効果がある。
◆ペアローン
一つの物件に対し、夫婦または親子が、それぞれ契約者として住宅ローンを組む方法。
それぞれが相手の連帯保証人になる。
「ペアローン」についてはこちらのコラムもご覧ください。
▶住宅ローンは何年で組んだらいい?~平均値でみる住宅ローン~
◆収入合算
一定の収入のある親族の収入を申込者(主債務者)の収入に合算して住宅ローンを組む方法。
収入合算者は、連帯保証人になることが必要。
◆連帯債務
1つのローンに対して債務者が複数人いることを意味し、連帯債務者はそれぞれがローン全体に対して責任を負う。
債権者は、全部の弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済の請求ができるが、1人が全部弁済すれば他の債務者の債務が消滅する。
まとめ
今回はちょっと分かりにくいけど知っておくと安心の不動産用語・略語についてご紹介させていただきました。少しでも参考になればと思います!
しかし、全部の不動産用語を網羅しているわけではないので、マイホーム探しの打ち合わせや、契約の中でわからない用語もあるかと思います。わからないまま「あの時確認すればよかったぁ…」と後悔するよりは、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥という言葉があるように、マイホームは一生に一度の大きな買い物になります。その場でわからない用語は、営業担当者に遠慮せず質問するようにしましょう。

株式会社フレンドホーム
経営企画部マーケティング課
増田 絵実
埼玉県北葛飾郡杉戸町在住。
子育てをしながら不動産業界で5年以上、営業サポートとして勤務。
物件のポータルサイト掲載や販促資料の作成など、営業活動を支える業務を幅広く担当。
これまでの経験を活かし、現在は「この街に住む人にとって、住む街がより魅力的なものになるように」をテーマに、賃貸・購入・売却に関する知識や、子育て世代ならではの視点を盛り込んだ不動産コラムを執筆。

