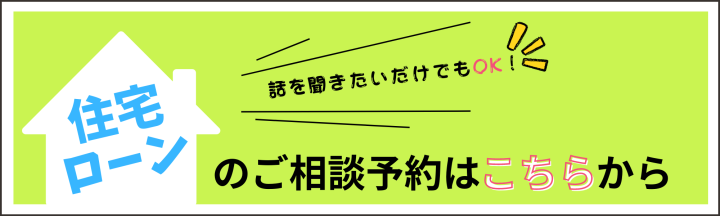住宅ローンは何年で組んだらいい?~平均値でみる住宅ローン~
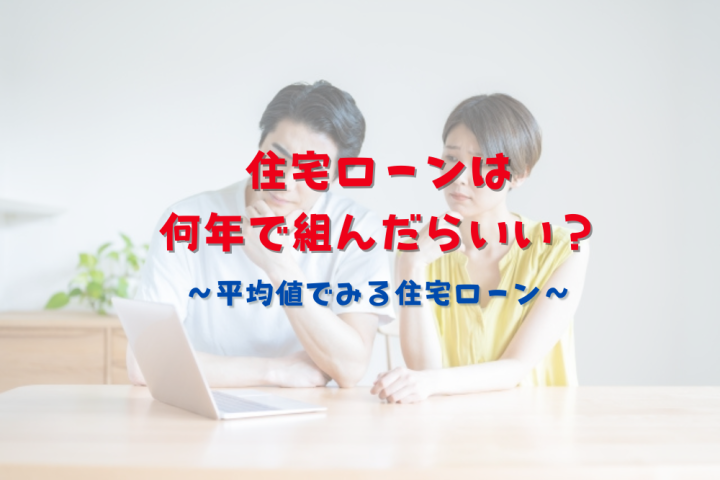
マイホーム購入を検討するうえで、住宅ローンの借入れを考えている方は、「借入年数を何年にするのか?」「何歳でローンを組むべきか?」など悩む人も多いことと思います。
ここでは国土交通省のデータを中心に、様々な平均値を紹介します。
無理のない住宅ローンを組むために、今回紹介したデータを参考にしてみてください。
目次
1:住宅ローンは何年が理想?
「住宅ローンの借入期間は何年くらいで組むもの?」と不安に思っている人もいらっしゃるかと思いますが、基本的には住宅ローンの借入期間は契約者が自由に設定できるものではありません。金融機関によって最長期間が設定されており、その範囲内で借入するようなかたちになります。
ここでは、金融機関の設定する最長期間の中でだいたい何年くらいで住宅ローンを返済しているのかをはじめ、住宅ローンの返済で重要となる「返済期間・返済月額・返済負担率」の3つの平均値を紹介していきます。日々の生活にとても影響がある数値ですのでよく考える必要があります。
2:住宅ローン借入時のさまざまな平均値
ここでは、住宅ローンを借入れるときのさまざまな平均金額を紹介します。
2.1:住宅ローンの平均借入金額

住宅購入のときには、頭金と銀行からの借入れを住宅購入資金に充てますが、ここでは、住宅ローンの平均借入金額を紹介します。
注文住宅:4,447万円(住宅建築資金、土地購入資金の合計平均)
戸建分譲住宅:3,160万円
中古戸建住宅:1,707万円
2.2:住宅ローンの平均世帯年収
住宅ローンを借入れするときの平均金額をみてきましたが、実際に住宅ローンを組むときには、平均年収はどれくらいなのでしょうか。
ここでも国土交通省のデータを参考にすると、注文住宅、分譲住宅は、住宅ローンを組むときの平均世帯年収は約600万円~800万円の割合が中心となっていて、中古住宅を購入する人の平均世帯年収は約400万~600万の割合が中心となっています。
この金額は世帯主だけの年収ではなく、世帯全員の年間収入の合計です。
最近では住宅ローンを組む世帯は共働き世帯が多く、夫婦の収入を合わせてローンを組むペアローンを利用しているのが特徴です。
ペアローンは、夫婦がそれぞれ1つずつローンを組み、2つのローンを一つの住宅の返済に充てることをいいます。ペアローンを利用する利点は、契約者ひとりだけの収入ではなく夫婦の収入を合算して借入れできるので、借入れ金額を増やすことができる点です。さらに、住宅ローン控除を2人分利用できるなどメリットがあります。
しかし、女性は妊娠や出産により収入が変動する可能性があります。ペアローンを利用するときは、2つのローンのうち1つのローンは、実際の収入の50%ぐらいを目安にすると安心です。
2.3:住宅ローンの借入時の平均年齢
住宅ローンを借入れるときの平均年齢は、全てのタイプの住宅で30代~40代です。住宅を購入をするときの平均年齢と同じような結果になっています。
3.住宅ローン返済の様々な平均値
ここでは、住宅ローンの返済のさまざまな平均金額を紹介します。
3.1:住宅ローンの平均返済期間

住宅ローンの平均返済期間をみていきたいと思います。
多くの金融機関が返済期間を最長35年としています。近年では他の金融機関と差別化を図る目的や多様なニーズに応えるため、返済期間を40年や50年としているプランを提供している金融機関もあります。
国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」から、住宅ローンの平均返済期間は、中古住宅が26.2年、分譲住宅が29.7年、注文住宅の32.7年となっています。
中古住宅も分譲住宅も、令和4年度に比べ返済期間が2年程短くなってきています。
少しでも早く住宅ローンの返済を済ませたいと思うものですが、返済期間は長ければ長いほど、月々の負担を軽くすることができます。
毎月の負担額を減らすことで、その分手元に残るお金は多くなります。想定外の出費にも対応できる資金を貯めておくことも大切です。
手元に残る金額が多い方がいいことはもちろんですが、住宅ローンは後から返済期間を延ばすことは難しいです。
そのため最初に組む際には最長で設定し、必要であれば後から繰上げ返済をする方法があります。繰り上げ返済で手数料を取られる場合もありますが、ほとんどの場合、利息を減らすことができローンの支払い期間は短くなります。
3.2:住宅ローンの月々の平均返済額
国土交通省のデータによると、注文住宅の年間返済額は平均155.2万円、分譲住宅が125.0万円、中古戸建が108.3万円となっています。
このデータから分譲住宅の毎月の返済額の平均はおよそ10万4,000円となります。ボーナスを返済にあてると月々の返済はもう少し抑えることができます。
3.3:住宅ローンの平均返済負担率
無理なく住宅ローンを返済するために重視すべき指標は返済負担率です。
返済負担率とは、年収に占める年間返済額の割合のことをいいます。金融機関が提供している借入可能金額のシミュレーションツールでは、額面年収の30%〜35%程度まで借入れ可能となっていることが多いです。しかし「借りられる金額」と「無理なく返済していける金額」は、大きく異なります。
国土交通省のデータによれば、返済負担率は注文住宅が19.4%、分譲住宅で17.6%、中古住宅で16.1%です。
一般的には20%から25%が無理のない返済負担率と考えられており、データではそれを下回る数値となっています。
借入れ限度額いっぱいでローンを組むと、先々、予測できないことが起こったときに対処できなくなります。子どもがいれば、成長するにつれ増えていく教育費のことを考える必要があります。また、年齢が上がれば介護資金も必要です。気持ちに余裕を持って生活できるように、無理のない返済負担率でローンを借入れるようにしましょう。
4:マイホーム購入事情
購入金額の平均を把握することで、どの程度の費用感で家を購入するのが一般的なのかがわかります。また、購入年齢を知ることで、どの年齢層がどのタイミングでマイホームを購入しているのか、ライフステージや経済状況を反映した傾向が見えてきます。
4.1:マイホームの平均購入金額は?
国土交通省のデータから、マイホームの平均購入価格を紹介します。
注文住宅:5,811万円(住宅建築資金、土地購入資金の合計平均)
戸建分譲住宅:4,290万円
中古戸建住宅:2,983万円
購入金額については購入予定のエリアによって金額が変わってきます。上記は全国平均なのでエリアによっては全国平均より高かったり低かったりすることもあります。あくまで目安として参考にして頂ければと思います。
4.2:マイホームの平均購入年齢
全てのタイプの住宅で、住宅を購入する人の平均年齢は30代が中心となっており、購入する平均年齢を見ると年代によって物件形態の好みが異なります。
若い世代では、中古物件より新築物件が好まれる傾向にあり、反対に、中古物件は50代〜60代の方に需要があります。
住宅ローンの完済年齢が、80歳までとしている金融機関が多いため、30代~40代であれば、団体信用生命保険への加入がしやすく長期間にわたって働けるため多額の住宅ローンを組めることが大きな理由です。
一方で、50代以降の人は子供も成長して住む人が減り、老後のことを考えて住宅をコンパクト化・簡略化する目的を持ちます。
定年までの返済期間を考え、いつごろの購入がベストなのか早めの計画が大事といえます。
5:まとめ
いかがだったでしょうか?
人生の一大イベントである、マイホームの購入にはさまざまな悩みがつきものです。
特にはじめて住宅ローンを組もうと思っている方はどれくらいの金額で何年くらいで組んでいるのか気になりますよね。
今回紹介した数値はあくまでも平均値ですので、参考程度にとらえて頂ければと思います。
実際に住宅ローンを組む際は、収入や生活のスタイルを十分に考慮して判断しましょう。
フレンドホーム売買センターでは資金シミュレーションが無料でご相談可能です。
他社様で住宅ローンを組めなかった方もフレンドホーム売買センター(0120-864-863)まで是非お気軽にご相談下さい!

株式会社フレンドホーム
経営企画部マーケティング課
増田 絵実
埼玉県北葛飾郡杉戸町在住。
子育てをしながら不動産業界で5年以上、営業サポートとして勤務。
物件のポータルサイト掲載や販促資料の作成など、営業活動を支える業務を幅広く担当。
これまでの経験を活かし、現在は「この街に住む人にとって、住む街がより魅力的なものになるように」をテーマに、賃貸・購入・売却に関する知識や、子育て世代ならではの視点を盛り込んだ不動産コラムを執筆。