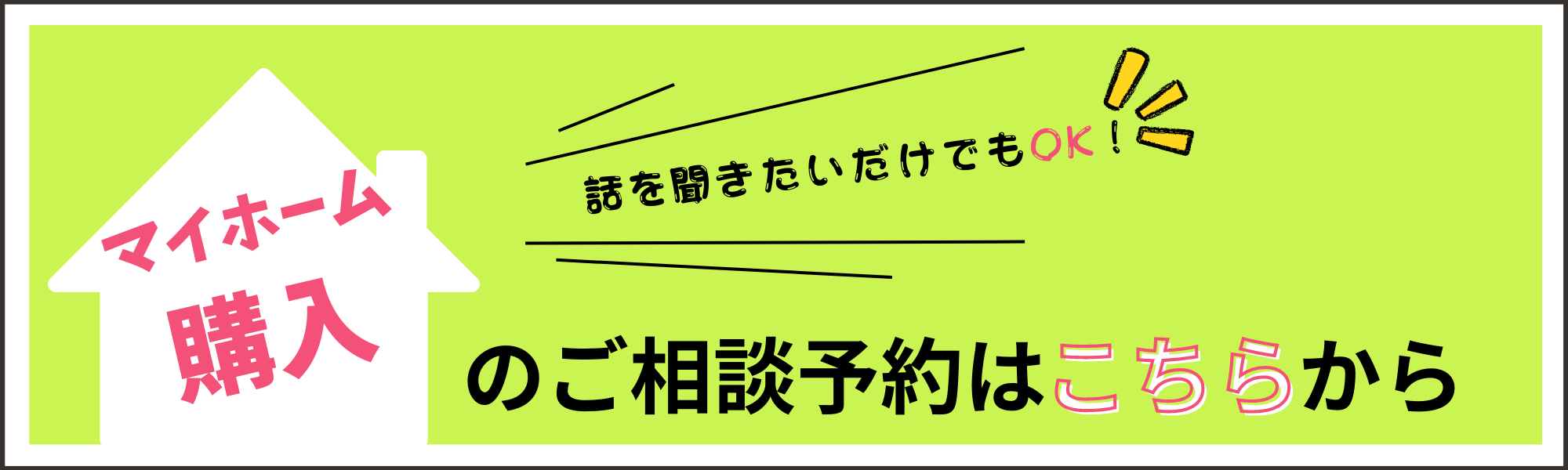地震がきても大丈夫?建売住宅の耐震性

南海トラフ地震や首都直下型地震など、大規模な地震の発生が今後も懸念されています。杉戸町周辺で家を探している方にとって、「地震に強い家かどうか?」は非常に重要なポイントです。
特に、コストパフォーマンスに優れた建売住宅を検討していると、「建売住宅って本当に耐震性があるの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、建売住宅の耐震性について基本からわかりやすく解説し、安心して住まい選びができるようお手伝いします。
1:耐震基準と耐震等級って何?
まず知っておきたいのは、日本の住宅はすべて「建築基準法」によって、最低限の耐震性を備えることが義務付けられているという点です。
住宅を新築で建てる場合はもちろん、中古住宅を購入する場合にも、「地震に強い家かどうか」を判断するための指標として重要なのが、「耐震基準」と「耐震等級」の2つです。
ここでは、この2つの指標の違いについてお伝えしていきます。
1.1:建築基準法の耐震基準

「耐震基準」とは、建物を建てる際に最低限満たすべき地震に対する安全性の基準であり、「建築基準法」によって定められています。
この基準の目的は、地震に対して建物が安全であること、かつ、建物内の人の命を守ることを目的に基準が決められています。
日本では、過去に多くの大地震によって住宅の倒壊被害が発生してきました。そのたびに法改正が行われ、耐震基準は段階的に強化されています。
【1981年(昭和56年)以前(旧耐震基準)】
「旧耐震基準」とは、「旧耐震」とも呼ばれ、1950年(昭和25年)に制定された基準です。
■耐震性能の目安
震度5強程度の地震に耐えられる設計
■課題
この基準では大地震に対する耐久性が十分でなく、阪神・淡路大震災(1995年)で多くの建物が倒壊した原因の一つとされています。
【1981年(昭和56)以降(新耐震基準)】
「新耐震基準」は、1981年(昭和56年)に制定され、旧耐震基準の安全基準を大幅に強化したものです。
■大きな変更点
震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないよう設計基準が強化されました。
■内容
建物の強さを計算する方法や、使う材料の強度、柱や梁(はり)のつなぎ目の作り方など、細かいルールが追加され、地震に耐える力が大きくアップしました。
■実績
この基準以降に建てられた建物は、1995年の阪神・淡路大震災など、後の大地震でも建物が倒壊した数が大幅に少なくなったという実績があります。
【2000年(平成12年)の改正】
2000年には、新耐震基準をさらに発展させる形で、建物の安全性をもっと詳しく・正確にチェックできるようにルールが見直されました。
■耐震設計の精密化
地震に対して建物がどれだけ強いかを、より細かく、現実的に評価できるようになりました。
■繰り返しの揺れや重みにも対応
地震は一度だけでなく何度も起きることがあります。また、建物は長い年月をかけて重さがかかり続けるものです。そうした繰り返す揺れや、長期間の重みにも耐えられる設計ルールが新たに加わりました。
■耐震性能表示の制度化
住宅性能表示制度の導入により、耐震等級を含む性能評価が明確化され、消費者が性能を比較しやすくなりました。
このように2000年の改正によって、住宅の耐震性能は1981年基準よりもさらに正確で高いレベルに進化しました。
現在の建売住宅は、この2000年基準にも対応しており、より安心して暮らせる家づくりが進んでいます。
1.2:耐震等級とは?
さらに、住宅の耐震性能をわかりやすく示す指標として「耐震等級」があります。これは住宅性能表示制度に基づき、耐震性を「等級1〜3」で評価します。
■等級1
建築基準法で定められた耐震性能と同等
震度5ではほとんど損傷はなく、数百年に一度起こる震度6強〜7に相当する大地震に耐えうる強度を持つよう構造計算されている。
地震後には大規模な修繕が必要だが、即倒壊はしないレベル。
■等級2
等級1の1.25倍の地震の力に耐えられる(学校や病院レベル)
保険料や税金の優遇を受けられる「長期優良住宅」として認定されるには耐震等級2以上の強度が必要。
地震後には一部修繕が必要だが、生活に支障がないレベル。
■等級3
等級1の1.5倍の地震の力に耐えられる(消防署や警察署レベル)
地震後もほとんど損傷がなく、すぐに生活できるレベル。
実は、建売住宅の中にも耐震等級2や3を取得している物件が多くあります。
2:建売住宅の耐震性は本当に大丈夫?
建売住宅の中には、びっくりするほど価格が安い物件もありますが、「耐震性は大丈夫なのかな・・・?」と不安を感じる人もいるかと思います。
上記でお伝えした通り、新築建売住宅を含む多くの住宅に対して、建築基準法により安全性や耐震性が保証されているので安心してください。
建売住宅が安い価格で販売できるのは設計や材料が規格化され、大量発注することでコストを抑えているからです。
地震が多い日本では、住宅を購入時に「地震に強い家かどうか?」は重要なポイントです。
3:地震に強い建売住宅を選ぶポイント

安心して暮らせる家を選ぶために、以下のポイントを必ずチェックしましょう。
■建築工法
・「在来工法」と「ツーバイフォー工法」が主流。
・2000年以降の法改正により、どちらも耐震性が十分に確保されている。
・ハウスメーカーごとに「耐震」「制震」の独自技術があるため、比較検討が重要。
■地盤調査・改良の有無
・地盤の強さは家の揺れやすさに直結。
・地盤調査が行われているか、必要なら改良工事がされているか確認。
■基礎の種類
・「ベタ基礎」は鉄筋コンクリートを全面に敷く構造で、地震や湿気に強い。
■建築確認済証・検査済証
・第三者機関のチェック済みであることを示す証明書。
・一定の安全性と品質の証となる。
■耐震等級の記載や証明書の有無
・「住宅性能評価書」に耐震等級(1〜3)が明記。
・等級が高いほど、大地震でも倒壊しにくい構造であることを示す。
よくある質問(Q&A)
Q1:建売住宅は地震に弱いですか?
A:いいえ。建築基準法を満たして建てられているため、一定の耐震性はあります。耐震等級を取得している物件も増えており、必ずしも弱いとは限りません。
Q2:注文住宅と建売住宅、どちらが安心ですか?
A:一概には言えません。建売住宅は品質が安定しやすく、注文住宅は設計や材料にこだわれます。重要なのは「何を重視するか」と「確認ポイントを押さえること」です。
Q3:外見だけで耐震性はわかりますか?
A:わかりません。図面や住宅性能評価書、第三者の検査結果を確認することが大切です。
Q4:購入後に耐震補強はできますか?
A:はい。筋交いの追加や制震装置の導入、家具の固定などがあります。既存住宅の耐震診断もおすすめです。
Q5:地震保険には加入したほうがいいですか?
A:はい。地震による損害は火災保険では補償されないため、備えとして加入をおすすめします。地震保険は必ず火災保険とセットでなければ加入できません。住宅ローンの条件として求められることも多いです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は建売住宅の耐震性についてお伝えしました。日本は地震が多いので耐震性は気になりますよね。
建売住宅でも耐震性に関する基準はしっかり守られており、安心して暮らせる物件がたくさんあります。大切なのは「何を確認すれば安心か」を知っておくことです。
フレンドホームでは杉戸町周辺の物件情報だけでなく、耐震性能についてのご相談やアドバイスも行っています。「こんなこと聞いても大丈夫?」というようなことでもお気軽にご相談ください♪

株式会社フレンドホーム
経営企画部マーケティング課
増田 絵実
埼玉県北葛飾郡杉戸町在住。
子育てをしながら不動産業界で5年以上、営業サポートとして勤務。
物件のポータルサイト掲載や販促資料の作成など、営業活動を支える業務を幅広く担当。
これまでの経験を活かし、現在は「この街に住む人にとって、住む街がより魅力的なものになるように」をテーマに、賃貸・購入・売却に関する知識や、子育て世代ならではの視点を盛り込んだ不動産コラムを執筆。