不動産購入で知るべき告知義務のポイント
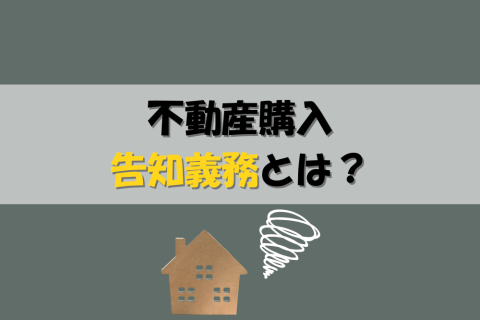
マイホーム購入を検討していると、物件情報に「告知義務あり」という表記を目にすることがありますよね。
「告知義務ってなに?」 「え、なにか隠された事情があるの?」と不安に感じる方も多いはずです。
今回は、「告知義務」の意味や注意点についてお伝えします。安心して物件を選べるよう、一緒にポイントを確認していきましょう。
目次
1:告知義務とは?

不動産を売却したり仲介したりする際には、買主にとって重要な情報を事前に伝える「告知義務」があります。
この義務は、宅地建物取引業法などに基づいて、売主や不動産会社に課せられているものです。
例えば、過去に室内で自殺や火災があった場合や、近隣に反社会的勢力が出入りしていたといった事実は、買主にとって物件の購入を判断する上で非常に大切な情報です。
このような「もし知っていれば購入を見送った可能性がある情報」を隠して契約してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
だからこそ、買主が納得して購入を判断できるように、告知義務として事前に正確な情報を伝えることが不動産取引の基本ルールとされています。
2:告知義務の具体的な内容とは?
では、具体的には告知義務の内容はどのようなものがあるのでしょうか。
代表的なものとして以下の4点があげられます。
2.1:心理的瑕疵(しんりてきかし)
告知義務の中でも、もっともイメージしやすく、不安を感じやすいのが心理的瑕疵です。
これは、物件自体に物理的な欠陥がなくても、過去の出来事や周囲の環境によって、心理的に嫌悪感を抱かれる可能性があるものを指します。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
・周囲に反社会的勢力が関係している
・近隣で凶悪事件があった
「この部屋で過去に事件があった」と聞けば、不安を感じる方は多いはずです。
実際に暮らすうえで問題がなくても、そういった背景を知っていたら選ばなかったかもしれないという判断は、買主にとって非常に重要なポイントです。
2.2:物理的瑕疵(ぶつりてきかし)
次に挙げられるのが、建物や土地そのものに問題がある物理的瑕疵です。
これは見た目だけではわからないことも多く、住み始めてから気づいて困るケースも少なくありません。
例えば、こんな状態が該当します。
・基礎や構造部分の欠陥
・排水設備の故障や土壌汚染
見た目はキレイな中古住宅でも、床下や壁の内部に問題が隠れていることもあります。
「住んでみたら雨が吹き込んできた」「異臭がするので調べたら排水設備が壊れていた」など、あとから大きな修繕費がかかることも。
だからこそ、こうした不具合がある場合は、事前に買主へ説明することが義務づけられているのです。
2.3:環境的瑕疵(かんきょうてきかし)
物件そのものに問題がなくても、周辺環境によって住みにくさを感じるケースがあります。これが、いわゆる環境的瑕疵です。
「住んでみたら、思っていた環境とまったく違った…」というトラブルの原因にもなりがちです。
例えば、以下のようなケースが該当します。
・騒音、悪臭、振動などの問題
・周辺に嫌悪施設(産業廃棄物処理場など)がある
こうした情報は、不動産広告や内見だけではわかりづらく、暮らし始めてから気づくことも多いのが実情です。
「昼間は静かだったのに、夜になると近くの施設の騒音がひどい…」
そんな後悔を防ぐためにも、売主や仲介業者には事前に買主へ説明する義務があります。
2.4:法的瑕疵(ほうてきかし)
見た目には問題がなくても、法律上の制限や権利関係の問題によって、自由に使えなかったり建て替えができなかったりする物件があります。これが法的瑕疵です。
例えば、以下のようなケースが該当します。
・法令による建築・利用制限
・借地権や抵当権など、第三者の権利が設定されている
・土地に未登記建物がある
例えば、「古家を解体して新築を建てたい」と思っていたのに、”実は接道条件を満たしていなかったため建て替えができなかった”というようなケースもあります。
法的瑕疵は、見た目や現況では判断しにくく、契約後にトラブルになるケースが多いため、事前の説明が不可欠です。
3:どこまでが「告知義務」?知らずに買ってしまう可能性は?
告知義務は、売主や仲介業者が“知っていた事実”に対してのみ課されるものです。
つまり、売主自身も知らなかった事実については、そもそも告知義務が発生しません。
また、かつては告知義務の対象とされていなかった内容が、後になって「本来は説明すべきだった」と判断されるようなケースもあります。こうした場合にも、当時の基準では義務がなかったため、結果的に告知されていなかったということが起こりえます。
こうした曖昧さを補うために参考になるのが、国土交通省が公表しているガイドラインです。
▶ 宅建業法施行規則の一部改正
4:告知義務のある物件を知らずに購入してしまったら?
購入したあとになって、「実は事故物件だった」「雨漏りの修繕歴があったのに聞いていなかった」といった重要な事実が後から発覚したら…?
そんなとき、買主には救済の手段があります。
その中でも特に重要なのが「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」というルールです。
これは、売買契約の内容と実際の物件の状態が大きく違っていた場合に、買主が売主に対して補償を請求したり、場合によっては契約解除を求めたりできるルールです。
詳しくは、こちらのコラムをご覧ください
▶ 契約不適合責任とは?どんなときに使えるの?
5:告知義務ありの物件=購入してはいけない?
「告知義務あり」と記載されている物件が、必ずしも悪いとは限りません。
・被害が軽微で修繕済み
・心理的瑕疵の内容が限定的
重要なのは「どんな事実が告知されているのか」を具体的に確認することです。
特に、心理的瑕疵については感じ方が人それぞれ異なるため、その内容をよく理解し、自分が納得できるなら購入しても問題ありません。
6:購入を検討する際のチェックポイント

不動産の購入は大きな買い物なので、安心して取引を進めるために、以下の点を確認しておくと安心です。
・補修・修繕の有無と内容
・近隣住民の雰囲気やトラブル履歴
・担当者に直接、詳細を質問する
不明点や不安がある場合は、不動産会社に遠慮なく相談することをおすすめします。
まとめ:正しく知れば、安心して購入できる
いかがでしたか?
「告知義務あり」という言葉に不安を感じる方は多いと思います。ですが、きちんと説明を受けて内容を理解できれば、納得して物件を選ぶことができます。
何より大切なのは、情報をオープンに伝えてくれる信頼できる不動産会社と出会うことです。フレンドホームでは、買主さまの不安に寄り添いながら、丁寧に物件のご案内を心がけています。
不動産購入に関して何か気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社フレンドホーム
経営企画部マーケティング課
増田 絵実
埼玉県北葛飾郡杉戸町在住。
子育てをしながら不動産業界で5年以上、営業サポートとして勤務。
物件のポータルサイト掲載や販促資料の作成など、営業活動を支える業務を幅広く担当。
これまでの経験を活かし、現在は「この街に住む人にとって、住む街がより魅力的なものになるように」をテーマに、賃貸・購入・売却に関する知識や、子育て世代ならではの視点を盛り込んだ不動産コラムを執筆。


