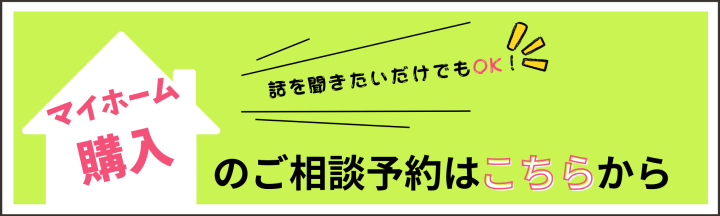隣の家との境界線「隣地境界線」とは?

中古住宅を探していると、まずは間取りや立地、日当たりや設備、そして室内の雰囲気に目を奪われてしまうものです。
「この家、素敵!」と思ったとき、そのまま契約に進みたくなりますよね。
でも実は、「お隣との境界」が曖昧なまま購入すると、後で思わぬトラブルになることがあります。
この記事では、隣地境界線の基本から確認のコツ、トラブル事例、そして防ぐための対策まで、わかりやすくご紹介します。
目次
1.隣地境界線ってなに?
「隣地境界線」とは、自分の土地とお隣の土地を分ける線のことです。
民法では、境界は境界標(杭など)で示すと決められていて、土地の権利を守る大切な役割を持っています。
境界は主に次のような方法で確認します。

◆境界標(境界杭)
コンクリートや金属、石などでできた杭が、敷地の角や辺の途中に埋められています。
◆地積測量図
法務局で手に入る図面で、境界標の位置や距離が記載されています。境界杭がなくなっていても、この図面があれば復元できます。
2.現地でチェックしたいポイント
中古住宅の内見の際には、こんなところをチェックしてみましょう。
① 境界杭があるかどうか
折れていたり地面に埋もれていないかも確認しましょう。もし境界杭が見つからない場合は、土地家屋調査士に依頼して位置を特定し、新たに設置する必要があります。測量にはお隣との立ち会いが必要で、費用は一般的に30万〜80万円ほどかかります。
② 地積測量図の有無
最新のものかどうかも大事です。古い図面は精度が低い場合や、実測と食い違うことがあります。
③お隣との認識の一致
売主や仲介業者に「隣の方とも境界について合意できていますか?」と聞いてみましょう。認識が食い違っている場合は、購入後にトラブルになるリスクがあります。
3.実際によくあるトラブル
・フェンスや塀の位置が間違っていた
購入後に測量したら、フェンスが隣地に越境していたことが発覚。撤去費用や補修費が発生するケースです。
・お隣からの越境
木の枝や屋根、雨どいなどが境界を越えている場合、切除や補修の費用負担でもめることがあります。
・契約後に面積差が判明
実測すると登記簿より土地が小さく、「思っていたより狭い」と感じるケースです。場合によっては資産価値にも影響します。
こうした事例は、国土交通省や不動産適正取引推進機構でも注意喚起されています。
4.トラブルを防ぐための3つのポイント
隣の家とのトラブルを防ぐための3つのポイントをご紹介します。
4.1.専門家に頼って境界をはっきりさせる

土地家屋調査士が、書類や現地を調べ、お隣の方と立ち会って境界を確定します。
その後、「確定測量図」と「筆界確認書」を作ってくれるので、将来の証拠にもなります。
4.2.契約の方法をチェックする
売買契約にはこんな種類があります。
実測・清算型
測量結果で面積差があれば代金を精算します。安心感は高め。
売買代金固定型
面積差があっても価格は変えません。早く契約を進められますが、差が大きいと損をすることも。
加えて、不動産会社(宅地建物取引業者)には、宅地建物取引業法第37条の2に基づく「境界明示義務」があります。これは、売買契約時に土地の境界線を明確に示し、境界標の有無や位置を説明する義務です。
ただし、この義務が課されるのは業者が売主となる場合に限られ、個人間売買では法律上の義務はありません。それでも、個人売主の場合でも境界をあいまいなままにすると、将来の越境や面積差をめぐるトラブルにつながる可能性が高くなります。
そのため、境界杭や地積測量図の提示がない場合は、測量を依頼し、書面で確認することが大切です。不安がある場合や境界があいまいな土地では、実測・清算型での契約を選ぶことをおすすめします。
4.3.公式資料を早めに確認
地積測量図や登記簿謄本は法務局で誰でも取れます。
購入を考えている段階でチェックしておくと安心です。
5.よくある質問(FAQ)
Q.境界杭が見つからない場合は?
A. 土地家屋調査士に依頼し、地積測量図やお隣との立会で復元できます。
Q.測量費用はどのくらい?
A. 土地の境界を確定させる測量の費用は、30万~80万円
Q.測量費用は誰が払うの?
A. 売主が負担するのが一般的ですが、折半や買主負担の場合もあります。契約前に確認しましょう。
Q.境界確定測量は絶対に必要?
A. 義務ではありませんが、境界があいまいだと将来トラブルになる可能性が高いです。
まとめ
いかがでしたか?
中古住宅の購入は、建物や立地の条件だけでなく、お隣との境界をはっきりさせることがとても大切です。境界杭や地積測量図を確認し、必要に応じて土地家屋調査士に測量を依頼しておくことで、購入後の安心感はぐっと高まります。
また、契約内容も境界や面積の扱い方をきちんと理解してからサインすることが、トラブルを防ぐ第一歩です。
お隣との境界は、家と同じく長く付き合っていくもの。購入前にしっかり確認しておけば、新しい暮らしを安心してスタートできます。

株式会社フレンドホーム
経営企画部マーケティング課
増田 絵実
埼玉県北葛飾郡杉戸町在住。
子育てをしながら不動産業界で5年以上、営業サポートとして勤務。
物件のポータルサイト掲載や販促資料の作成など、営業活動を支える業務を幅広く担当。
これまでの経験を活かし、現在は「この街に住む人にとって、住む街がより魅力的なものになるように」をテーマに、賃貸・購入・売却に関する知識や、子育て世代ならではの視点を盛り込んだ不動産コラムを執筆。